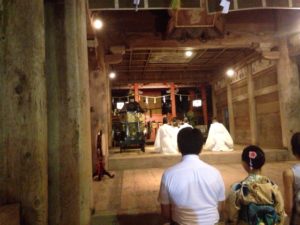先週末の25日、今週日曜日の26日、門田隆将さんの講演を聞きに行っておりました。
素晴らしい内容でしたので、その概略について紹介したいと思います。
25日@高知城ホール
「特攻、その真実」
わかる人にはわかる会場です。主催は高知大学の先生、教育学部 加藤誠之准教授です。
まず主催者挨拶として加藤先生からお話がありました。
・永遠の0が大ヒットした
・高知大学の学生たちにも大ウケ
・特攻隊の姿に感動した、お陰様で今があるとの感想
・この生徒たちの反応に危機感を抱く
・戦争の記憶が風化し
・戦争を美化する傾向にあるのではないか
・本講演を通して、特攻、その真実について触れ、多様な角度から検証することにより
・この流れに歯止めをかけたい
といった趣旨だったと思います。(この導入に怒った人が何人か帰ったようです)
そのお話の後に、満を持して門田隆将さんの講演。
ジャーナリスト門田さんが良い取材をするためにまず心がけることは、取材時には対象者のお話くださっている時間と空間に身を投じることだそうです。
今回のお話をするにあたっても、特攻隊員の生き残り、あるいは関係施設で働いていた方に直接インタビューを行いました。その際には今日の価値観を捨て去って、当時の人が何を見て聞いて感じたか、これをできるだけ忠実に追体験・再現できるよう心がけます。
さて、本題の特攻のお話ですが、
平成26年10月25日は、フィリピン、マバラカット基地から敷島隊による最初の神風特別攻撃が行われてからちょうど70周忌にあたる日。
まず特攻の前段として理解しておかなくてはいけない当時の背景は、日本軍の劣勢はもとより航空機パイロットの練度が極端に低下をしていたこと。マリアナ沖海戦、フロリダ沖海戦などでたくさんの熟練パイロットが失われていたこと。レイテ沖海戦では、海上で戦うことを前提に訓練をされていない陸軍の航空パイロットが投入されたほどの人材不足であった。天文航法によって水平や位置を把握する海軍に対して、陸軍は地文航法を採用していたため、海上で天地や方位の感覚を失ってしまい、敵機に七面鳥撃ちと呼ばれたように容易に撃墜されてしまったり、洋上に墜落することがあったということなど。
こういった背景のもと、空母への最も有効な打撃を与える方法はこれしかないということで、神風特別攻撃隊が編成されることになった。マバラカット基地で編隊を命ぜられた玉井浅一中佐のもと、甲飛10期生33名に対し、「25 番(250 ㌔爆弾)を零戦にハンダ付けして、貴様たち突っ込んでくれ」と志願が募られる。(ハンダ付けとは暗喩であって本当にハンダ付けをしたわけではない。)門田さんのインタビューによると、実際には候補者は40名程度いたとされ、その誰もが特攻の希望者を募った際には押し黙ったそうだ。その後しばらくの間を置いて、半ば雰囲気に圧された形で志願者の手があがると、上官から間髪入れずによしわかった、よろしく頼むという旨の締めの言葉があったとのこと。
神風特別攻撃隊の出だしは順調ではなく、最初の2度の出撃は空振りに終わっている。敵艦発見の報がもたらされても、特攻隊が現地に到着する数時間後には敵艦隊を見失ってしまっていたのである。軍上層部の中に特攻隊に対する冷ややかな声があがりはじめた頃、三度目の出撃にて関大尉率いる敷島隊による初の特攻がなされた。(最初の特攻が関大尉率いる敷島隊かどうかには異論もあるようです)
この第一次特攻隊には高知出身者が3名含まれており、その中の宮川正さんには豪快な逸話が遺されています。宮川さんは、周囲の張り詰めた空気の中にもかかわらず、自分は無駄死をしたくないのでどのような飛行方法が最も特攻の成功確率が高いか、みなさんの意見を聞かせていただきたいと周囲に相談したという。
戦後教育の中で、世間一般には、特攻とは天皇陛下万歳といった掛け声のもとに、悠久の大義のために、国家のために特攻がなされたと理解されているようですが、必ずしもそうではないと。関大尉におかれては、特別攻撃隊の編成の決まった20日の晩の記者取材に対して、「俺みたいな優秀なパイロットを殺してしまうなんて、もう日本はだめなんだ。もう日本はお終いだよ」そして「俺は天皇のためとか、国のために行くんじゃない。もし日本が負けたら妻が米兵に暴行されるかもしれない。だから俺は彼女を守るために行くんだ。どうだ、素晴らしいだろう。」と返答している。
さまざまな事情によって生き残られた特攻隊員に対して取材を行った際には、関大尉同様に、家族のためにいったのだという話が大勢を占めたそうです。
それともうひとつ。当時の特別攻撃隊は十代後半から20代前半の学徒出陣によって徴兵された人々が多く参加していました。旧帝大等に在籍していた彼らは、今よりもはるかに厳しい受験戦争をくぐり抜けた、同世代上位0.4%のエリートによって構成されています。親の溺愛も今以上であり、入隊式には家族が大挙して押し寄せるということで、巷の混乱を避けるために陸軍と海軍の入隊式の日を数日ずらしたほどです。さらには、艦船に配備された息子可愛さに、上陸の自由時間を少しでも長く一緒にすごすべく、海軍基地周辺に母親などが下宿をしていたこともあったそうな。そのような環境下にあった学徒たちがどのような気持ちでこの戦争、特攻に臨んだのかということには、門田さんも大変興味を惹かれインタビューを行います。
まず、彼らの多くは反戦であった。頭脳明晰な彼らからすれば戦争などするべきではないとの結論に至るのは当然のこと。それでもなぜ戦地に赴いたのかと聞くと、この戦争に負けたならば、白人がこれまでアジアやってきた過酷な植民地支配が日本にも及ぶからだと答えた。有色人種を動物としか考えていない白人から、家族を守るためには戦うしかなかった。年老いた両親を、まして自分より幼い弟、妹達を戦場におくることはありえず、自分がいくしかないのだと。そして、中でも最も頭脳明晰で操縦技術の巧みな人間から死地に赴いくことになる。特攻の生き証人はその方々に対して本当に申し訳ないと涙を流しながら語ったそうだ。
もうひとつ。元山航空隊 第一 七生隊の宮武信夫大尉(隊長)と日系二世の松藤大治少尉のお話。松藤少尉は日系二世として生まれ、小学校までアメリカにて過ごす。二重国籍であり、徴兵を断ることができるにもかかわらず(日系で断った人はいる)、彼はこれを受け入れた。
朝鮮の元山航空隊に配属されたのちは、持ち前の運動神経と頭の良さでメキメキと操縦の腕をあげ、宮武信夫大尉と並ぶまでになる。宮武大尉に寵愛された彼は、大尉が「俺は特攻に行く。お前たちもついて来い」と言うと、すかさずこれに応じたそうな。彼だけでなく、生徒たちは特攻という思想には賛同できないものの、大尉にはついていきたいと答えた。
「日本は戦争に負ける。でも、俺は日本の後輩のために死ぬんだ」
松藤少尉が福岡の親戚に残した言葉。
特攻の前夜、人々が落ち着かないままでいると、身長183センチの松藤が大きなヤカンを2つ提げてやってきた。中にはお酒が入っており、人々は最後の盃を交わしたのだった。眠れるものもいれば、そうでないものもいた。彼なりの気遣いであった。
出撃の朝、整備兵が資材の木をプロペラにぶつけてしまい、片岡機が飛べなくなるアクシデントに見舞われる。片岡氏を残して、七生隊はつぎつぎに空に飛び立つ。そらをおおわんばかりの特攻機の姿を見て、片岡氏は実に立派、実にあっぱれと感じ、勝てるはずのない戦争にひょっとして勝てるのではないかとの錯覚をおぼえたそうだ。
4月6日、七生隊は沖縄の海にて、米軍艦隊34隻に損害を与えた。
話は遡るが、宮武信夫大尉は、出発前に自由行動を許された際に実家に足を向けたことがあった。家族からどうしてもと一筆(いわゆる絶筆)を依頼されると、彼の書いた文字は「断」の一文字であったという。将来の夢、家族や友人、さまざまな物を断っていくという壮絶な決意が伝わってくる。
特攻ののちに、宮武信夫大尉の遺品が遺族に返されることがあった。遺品の中に一つだけ足りないものがあることに気付いたそうだが、それは以前渡してあった母親の写真とのこと。彼は母親の写真とともに沖縄の海に向かい、特攻し、その命を散らしたのであった。その母親からは、門田隆将氏が太平洋戦争 最後の証言 第一部 零戦特攻編を出版した際に電話があった。作中に息子、宮武信夫の名前があることを人づてに知った母は、居ても立ってもいられず、門田氏に電話をし、「お陰様で息子の最後を知ることができました」とお礼を伝えたのであった。
時代は流れ、平成5年のこと。
元山航空基地で松藤少尉と日々を過ごした大之木氏という方(ちなみに門田氏は彼を通じて松藤少尉を知る)。彼は、松藤少尉の母、ヨシノさんがロスアンゼルスでご存命であること知ると、渡米を決意。彼は、昭和20年4月3日の最後の晩の松藤少尉の姿を、ヨシノさんに伝えに行ったのでした。
大之木氏の話を黙って聞いていたヨシノさんは、彼の話が終わると、
「男というものは、そういうもんです。国の大事には男はキパッとやらにゃ。大治は立派なことをして死んだんです。そうじゃないですか?大之木さん」車椅子に腰かけたまま、そう問いかけました。大之木氏はその瞬間、「ハイッ」と言って立ちあがって頭を下げたそうです。
大之木氏は言う、
「私たちは、たまたま1945年のあの時に軍人であり、若者でした。私は、戦友たちの死を無意味だったとか、可哀相だったとか、そういうことは言って欲しくないんです。ただ、ご苦労さん、よくやったとだけ、言ってやって欲しいです。」
以上、門田隆将氏講演「特攻、その真実」のおおまかなまとめです。少し調べて加筆してあったり、語尾が不統一であったりします。また何分、私の文章力が未熟なもので、伝えるべきことを伝えきれていないかもしれませんがご容赦ください。門田隆将氏が本当に言いたかったことは、翌日26日の講演の内容とあわせたときに、その輪郭がよりくっきりとします。また余力あるときに書きたいと思います。
長文失礼しました。